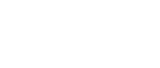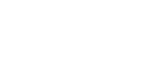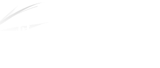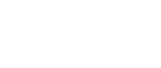甲冑は、日本の伝統的な武具の1つで、頭を守る「兜」と胴体を守る「鎧」をひとまとめにした名称です。本来は戦いにおいて身を守るためのものでしたが、現代では工芸品、古美術、歴史的な資料といった側面で高い評価を受けています。
甲冑の買取は、甲冑が持つ歴史的価値や甲冑の所持者、揃っている部品などによって大きく上下します。
今回の骨董品買取コラムでは「甲冑」の買い取りから甲冑の魅力や歴史、甲冑ついてご紹介します。ぜひ最後までお読みください。
甲冑の魅力
国宝や重要文化財になっている甲冑は多く、国宝には歴史の古い大鎧などが多くなってます。
一方の重要文化財には徳川家康や伊達政宗といった著名な武将が使っていた甲冑が多くなっています。
こうした甲冑には、さまざまな装飾が加えられており美術品的な要素も兼ね備えています。
戦国時代以降の甲冑は「当世具足」と呼ばれておりこうした種類の甲冑は、特徴的な兜の前立てでも有名です。
時代の移り変わりと共に、前立てや胴体への装飾は意匠がこらされたものへとなっていきました。
これは戦の場で目立ち、戦での戦功が甲冑を一目見ただけで分かるようにするためと言われています。
こうした時代の変化によって起きた甲冑への変化が、近年の甲冑の美術品としての価値を確立したとも言えます。
そして、甲冑は己の身を守るための道具であるため時代の最先端の技術を持って作られています。
木工、皮革、鈑金など様々な技術の粋を集め作られたものであるため、その時代を知るための歴史的資料、工芸品としての側面も強いのです。
甲冑の歴史
甲冑の歴史は古く、最も古い甲冑と言われているのが弥生時代に使われたものとされています。
木甲と呼ばれるこちらの甲冑は木で作られたもので、非常に簡素なものでした。
その後、金属の板をつなぎ合わせた甲冑が作られ、更に沢山の小さな鉄の板をつないだ甲冑も登場します。
その後、唐との行き来がなくなった日本では、独自の甲冑が登場します。
それが国宝にもなっている「大鎧」です。
大鎧は平安時代に生まれ、当時の戦の基本戦術だった馬に乗って弓を射る戦いに対して特化した鎧となっています。
この大鎧は地位の高い武士が身に付け、地位の低い武士は徒歩での戦が基本であったため歩きやすさを重視した「胴丸」と呼ばれる鎧が基本となっていました。
その後、時代の変化と共に戦で使われる武具も槍や鉄砲へと変化します。
こうした槍や鉄砲に対する甲冑として登場したのが当世具足です。
これらの大鎧、胴丸、当世具足は骨董品としても非常に高額で取引されています。
甲冑の様々な部品について

甲冑は鎧と兜以外にも、さまざまなパーツによって成り立っています。
顔を覆う面頬や兜の左右に立てる脇立、袖や脛当など種類も多く、揃っている部品の数によっても甲冑としての価値は上下します。
また、甲冑だけでなく甲冑を入れるための鎧櫃と呼ばれる箱の有無によっても価値は変化します。
甲冑の買取を依頼する場合には、まずこうしたパーツの有無などを十分に確認することが重要です。
甲冑の価値と買取り
甲冑の価値は、甲冑の保存状態や使っていた人によって大きく左右されます。
また、甲冑の歴史は古く買取している業者は、そこまで多くないため適切な鑑定を行える鑑定士を有した買取業者に買取を依頼することが大切です。