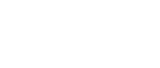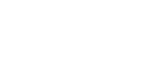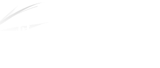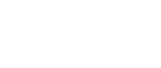茶杓(ちゃしゃく)とは、抹茶を茶器からすくいとる小さなさじのことで、茶道具で重要なアイテムのひとつです。
表千家、裏千家、武者小路千家といった三千家の有名な茶人が作った茶杓を買取に出せば、高価買取されることも珍しくありません。
今回の骨董品買取コラムでは、茶杓の買い取り、茶杓の魅力や歴史、武将の茶杓についてご紹介します。最後までぜひご覧ください。
茶杓の魅力
数ある茶道具のなかで茶杓は唯一茶人の手によって作られた道具です。
一見するとただの曲がった竹の棒で、作者はおろか時代すらもわかりにくいものです。
しかし、付属する筒や箱、銘とともに拝見すると不思議と作者の人間性や心の一端が見えてくるような感覚になります。
茶人の心に触れる。これが茶杓の最大の魅力でしょう。
茶杓の歴史
茶杓の起源は「則」、「匙」、「杓」などとよばれた茶の分量を量る計器になります。
金属や象牙、竹などの素材があり当時の中国から喫茶の文化とともに輸入されました。
日本では象牙と竹の茶杓が取り入られ、竹製のものが一般化しました。
茶杓は、茶の湯草創期の室町時代から道具として重要視され足利義政や珠光、珠徳の作と言われるものが伝わっています。
室町時代の代表的な削り師であった珠徳の茶杓は節なしが主であり、利休の師である武野紹鴎の時代には節止めや下がり節ののものが誕生しました。
しかし、利休によって節を中心に置く中節の形が定められると以降この形が茶杓の主流となり現代に至ります。
武将の茶杓
 桃山時代の茶杓は、他の美術工芸品と同じく特徴的です。
桃山時代の茶杓は、他の美術工芸品と同じく特徴的です。
古田織部や織田有楽斎など、桃山時代に活躍した武将茶人の茶杓を拝見すると形状や削り方は異なりますが唯一共通していたことは櫂先に力強さを感じるということでした。
江戸時代の茶人の茶杓を見ると櫂先の力強さはなくなり、端正で静かなものになります。
桃山時代は戦国時代終焉の時代でもあります。
武将の茶杓を手に取ると、戦に明け暮れ時代の転換期に生きた武将達の創作意欲と溢れんばかりのエネルギーが茶杓にも乗り移ったかのような印象を受けます
茶杓の価値と買い取り
昔から「茶杓は筒で買え」と言われています。
茶杓そのものには銘などがないため、作者の判別は非常に難しいのが実情です。
しかし、筒には作者本人や近しい人の筒書きがあるため、真贋を見極める重要なポイントとなります。
箱や添え状なども同様です。
どんなに素晴らしい茶杓でも裸では価値が付きませんので、茶杓を売買されるときは筒や箱が揃っているかしっかりと確認することをお勧めします。